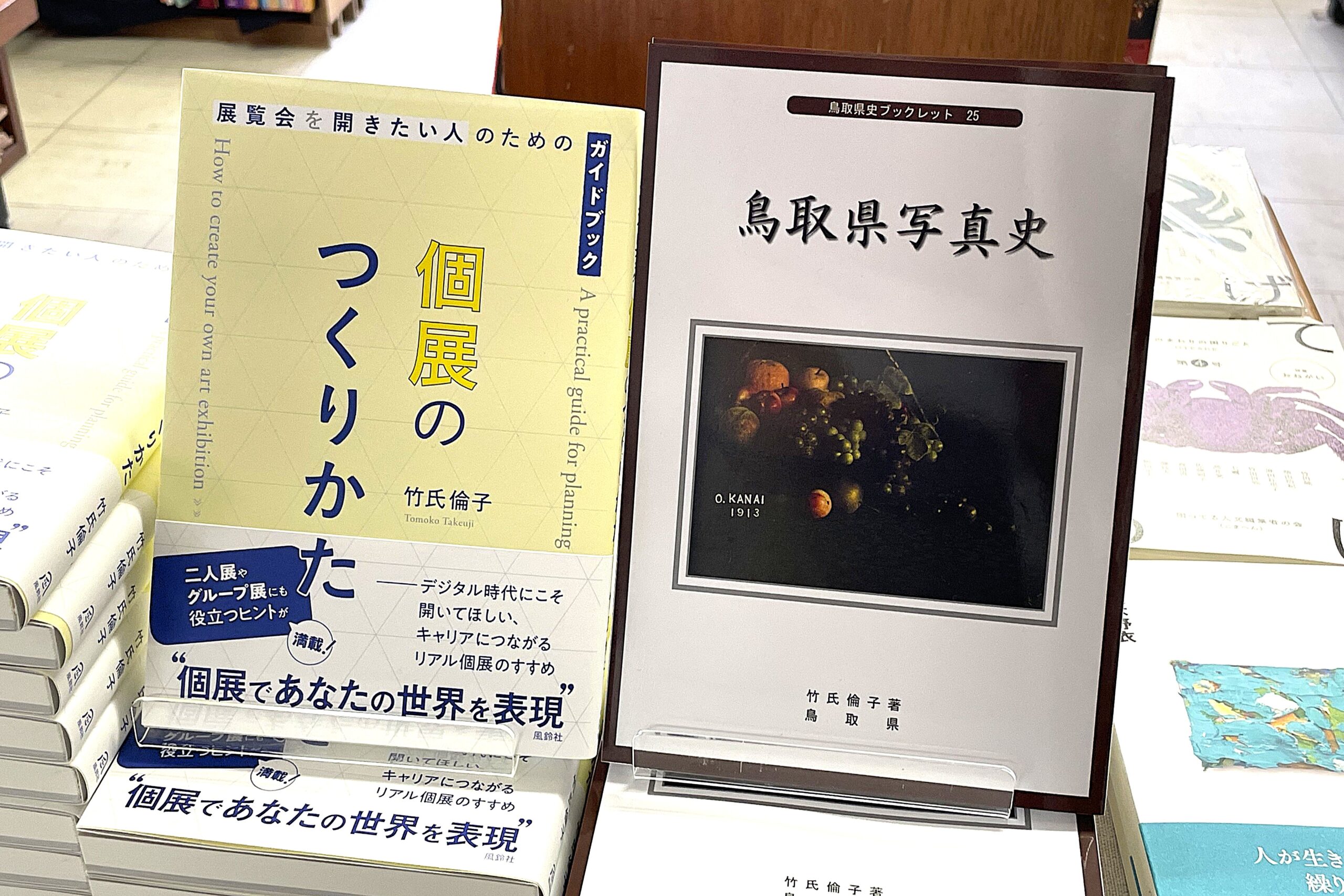地域の創造活動と歴史を結ぶ:竹氏倫子さんの新著2冊を読む
鳥取在住の美術史研究者・竹氏倫子さんの新著、『個展のつくりかた』(風鈴社)と『鳥取県写真史』(鳥取県立公文書館)が相次いで刊行されました。
鳥取県立博物館で2013年まで主任学芸員(美術担当)を務め、現在は在野の研究者として活動する竹氏倫子さんが、ほぼ同時期に本を2冊出版されました。1冊は初の商業出版となる『個展のつくりかた』。もう1冊は、これまでの研究を元に書かれた『鳥取県写真史』。
一見すると異なるテーマのように見えますが、作家として活動を続ける意義や、それを支える周囲の存在、芸術文化を次の世代につなげるという思いは共通しています。
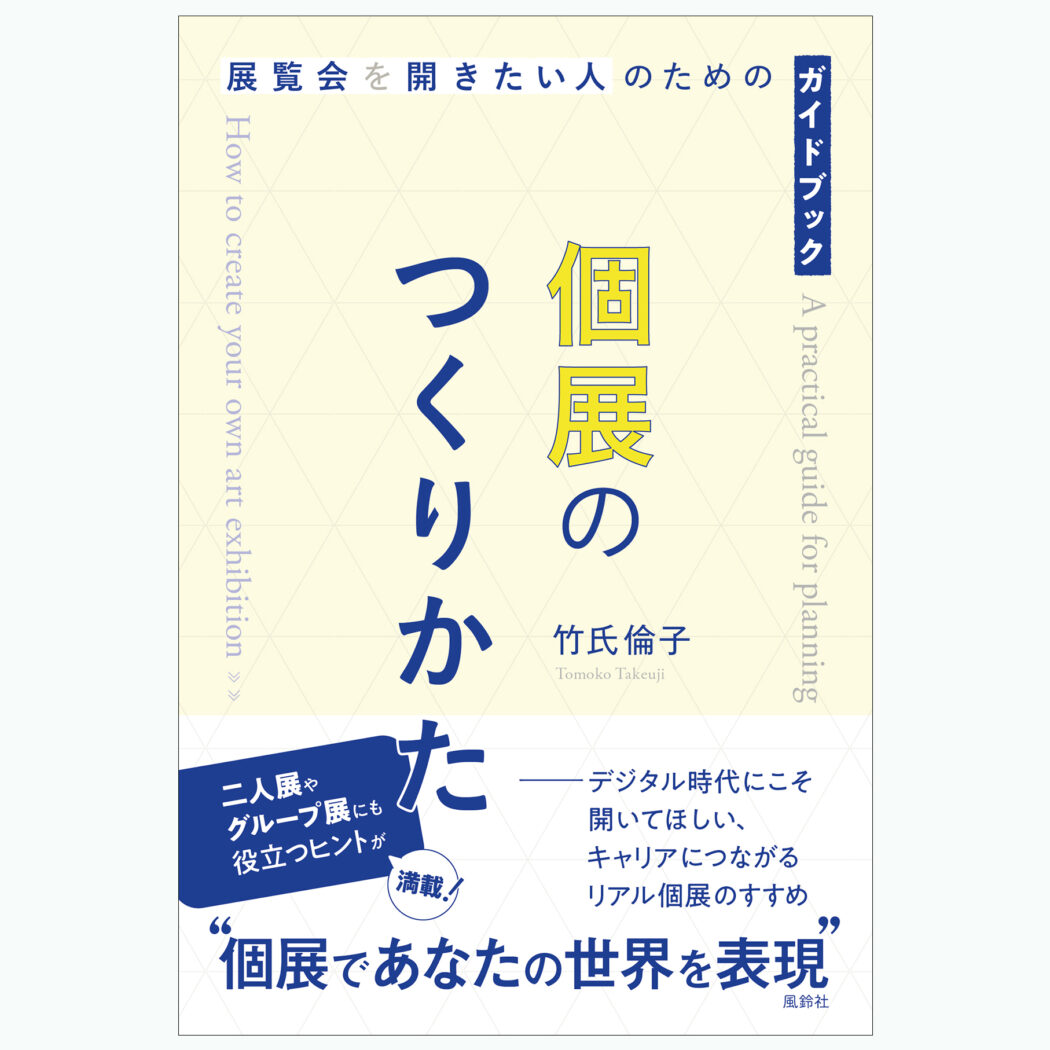
まず『個展のつくりかた』は、絵画や写真、イラストなどの制作活動をしている人が展覧会を開催するためのプロセスやポイントをまとめた、実践的なガイドブックです。
展覧会はただ作品を並べるだけのものではなく、それ自体が創造的な表現方法です。そのために、コンセプトをしっかりと言語化することの重要性が説かれています。「言語化」は、DMやステートメント、作品のキャプション制作においても必要となってきます。
作品のサイズや展示する数についての具体的な数字を用いた説明から、在廊中の来場者とのコミュニケーションで気を付ける点(否定しない、かつ気にしすぎない)、さらには「いただいたお花にはちゃんと水やりをしましょう」といった気配りまで、展覧会に関わるたくさんのプロセスが丁寧に解説されています。
初めて個展を開く作家がギャラリーオーナーや作家仲間、師事する先生など周りの人たちに頼る大切さを説きつつ、「最終的に判断は自分自身で行うべきだ」と主体性を重んじる姿勢に、本書の意図が表されているように思います。
さらに「個展を開いて変わること」をテーマにした対談も収録されています。イラストレーター Claraさん、日本山岳写真協会員・時本景亮さんのお話はもちろん、県内の作家を長く支えてきたギャラリーそらの安井敏恵さんと池田真木さんとの対談は、地域に根差した視線を感じさせる内容です。
また、展覧会がどんなプロセスを経て開催されるのか、どのような意図があるのかが書かれているので、本書を読めば、作家だけでなく鑑賞する側も展覧会をより楽しむことができます。
一方の『鳥取県写真史』は、鳥取県に写真がもたらされた明治初めから平成までの、本県の写真状況をわかりやすく解説しています。
国際的に高い評価を得ている塩谷定好や植田正治といった著名な写真家たちの活動や、その前史となる大正時代から続くアマチュア写真サークルの取り組み、土門拳と鳥取との関わりなども描かれています。
国内外の写真家に影響を受け、新しい表現方法を自家薬籠中の物にしようと切磋琢磨するも、戦争により分断され、なおかつその戦争に加担せざるを得なくなります。しかし戦後はさまざまな困難を乗り越えて、この流れが受け継がれていきます。
本書を読み進める中で特に感銘を受けたのは、地域の老舗である金居商店がプロアマ問わず写真愛好家を長年にわたり支えたという部分です。
鳥取の写真文化の発展に極めて重要な役割を果たしてきた、まさに”聖地”とも言えるお店が今もこの地で営業されています。
本書の後半では、2016年に「写真の町東川賞 飛騨野数右衛門賞」を受賞した池本喜巳が「池本喜巳小さな写真美術館」を開設したことにふれ、今も鳥取の写真文化が引き継がれていることを示しています。
竹氏倫子さんが今回刊行された2冊、一方は地域に根差した創造活動を後押しする実践的な本であり、もう一方は文化的な土壌を育んだ歴史を丁寧かつコンパクトにまとめています。この2冊を通じて、竹氏さんは鳥取の芸術文化の過去・現在・未来を伝えようとしています。
創造活動に関わる人、地域文化に関心のある人にとって、この2冊は多くの示唆を与えてくれるでしょう。
『個展のつくりかた 展覧会を開きたい人のためのガイドブック』
著/文|竹氏 倫子
発行|風鈴社
定価| 2,000円+税
ISBN|978-4-910795-02-7
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784910795027
『鳥取県史ブックレット25「鳥取県写真史」』
著|竹氏 倫子
発行|鳥取県立公文書館
定価| 500円
https://www.pref.tottori.lg.jp/321696.htm
竹氏 倫子 / Tomoko Takeuji
1972年埼玉県生まれ。鳥取県在住。鳥取県教育委員会美術館開設準備室学芸員を経て、2013年まで鳥取県立博物館主任学芸員(美術担当)。近代洋画、写真、西洋美術に関する展覧会の企画・運営、植田正治、前田寛治等の作家研究を行う。2014年より個人として美術・写真に関する論考や新聞連載を執筆するとともに、油彩画を制作し、絵画・彫刻グループに所属して発表活動を続けている。その過程で多くの作家や作家志望の人々に出会い、展覧会に関するノウハウを広く伝える必要性を感じ、本書の執筆に至る。